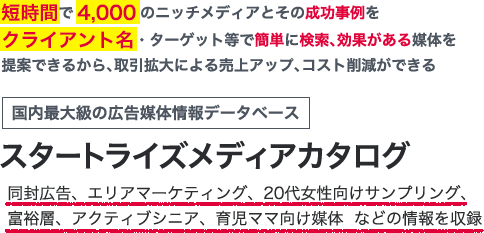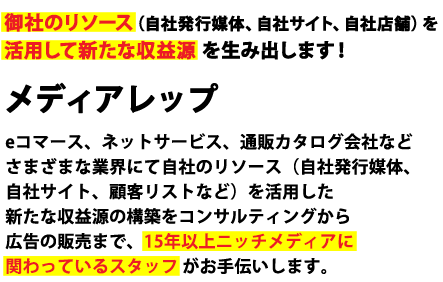第2回:「あなたの会社や商品をブランド化するための本の出し方、使い方 ~戦略的商業出版のすすめ~」
今回は、あなたの会社をブランドにして、ビジネスを拡大させるために出版をうまく使いましょう、というお話です。
ここでの出版は、「自費出版」のことではありません。出版社から商業的に本を出してもらい、それを自社でどうビジネスに活かすのか、ということです。
今回の講師は、株式会社自分楽 代表取締役、静岡大学大学院客員教授の崎山みゆきさんです。
崎山さんは、これまで出版社に企画を11件持ち込み、成功率100%、という方です。
崎山さんの出版企画には、いったいどのような特徴があるのでしょうか?
下記をご覧ください。
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
…………………………………………………………………………………………..
1.こんな人は、本を出してはいけない。
…………………………………………………………………………………………..
「本でも出そうかな」、「お金がかかるし」、「書く事がない」、「印税で楽がしたい」、「私のでは、売れないかもしれない」、
こんなセリフを口にする方たちには、私はやんわりと諭します。
「あ…やめた方がいいかもしれませんね」、「私は、強くおススメはしませんよ」
本当は、やんわりではなく「やめんか~コラッ」という気持ちですが、一応女性なので…。
本を出してはいけない人の共通点を、二つ挙げます。
一つ目は、本は簡単に出せると考えている人。
「本でも出そうかな」なんて、とんでもない! こういうことを言う方に限って、具体的なコンテンツがなく一冊になりません。「マーケティングの本でも出してみたい」という方が多いのですが、誰に向けて何をどのようなタイミングで発売すると、どれだけの収益がでるのかを、すらすらと話すことができないような人はダメです。
また、一冊出すために出版社は300万円ほどのリスクを負って勝負をします。紙、デザイン、ライティング、間接人員…これを知っていたら「本でも~」は失礼です。
二つ目は、熱意が続かない人。
本を出すには、執筆速度にもよりますが、概ね10カ月程度かかります。この間に、熱意が冷めてしまっては困ります。苦い思い出として、企画会議までいったにもかかわらず「やっぱり、やめます」と言われ、出版社に謝りに走ったという困った経験があります。
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.今やっていること、考えていることを書くと失敗する。
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
今、男性向けエステをやっているという人が、一年後に、高齢社会を先取りして、70代富裕層マダム対象に市場転換したいという方の場合、どのような本を出したらよいのでしょうか? 答は、男性向けではなく、70代富裕層マダム向けです。
大抵の出版プロデューサーは、今やっていることを本にして…と持ちかけますが、実はこの考え方はダメ!
本が出るまでに一年弱。
出版した時には、対象顧客が変わっているので、本の内容と顧客がマッチせず売れない本になります。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.文章下手でも何とかなる。肝心なのは出版企画 ! 企画がダメだと絶望的!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
文章が下手だから、本なんて…という方がいます。
しかし、全部の原稿を持ち込むなど、今や絶滅に近い!! 1-2枚の企画書を作成し、後から原稿執筆です。
よって、まず重要なのは企画書です。
私のところに相談に来られたイメージコンサルタントの女性は二年間、洋服の着こなし・マナーという企画で出版社を当たっていましたが、類書が多い、CA(キャビンアテンダント)に負けると、全くダメでした。
しかし、私は二カ月で企画を通して商業出版させました。そのコツは、「生き方の」イメージアップ、ブランディングという切り口です。
彼女の国際ボランティア経験、主婦から国際イメージコンサルタント日本代表に成長した経緯などを訴求しました。これには出版社も大喜び。
ナント!! 丸の内で平積みを果たしました。
もう一つの事例です。
文章下手を解消することが先決と、作家の方について勉強している方のケースです。
伝統ある自社商品をアピールしたいので、きちんとした文章が書けないといけないと言うのです。
私が企画書を作成するから、その間に自分で文章の書き方講座で勉強した方が、早いと言いましたが、耳を貸さず…。
あれから二年半経ちましたが、未だに作家先生のもとに通っています。
目的は何だったのか??
文章を書く暇がない、苦手という場合にはライターをつければ大丈夫です。
出版社がつけてくれる場合と、自分で雇う場合があります。ライター代は概ね40万~50万円。
レベルは金額に比例すると言われています。
また、自分の専門分野に疎い方に依頼すると、結局自分が書き直しということになりますので、
人選には細心の注意が必要です。
………………………………………………………………………………………………..
4.通る企画書、通らない企画書
……………………………………………………………………………………………….
では、通る企画書のコツは何かというと、ズバリ、市場調査と販促計画です。
出版社は本を出すのに一冊300万円のリスクを負うと言われています。
よってこの金額が回収出来ないような企画は、絶対に通りません。
新商品やサービスを世に送り出すときと同じです。
前者については、インターネット検索ではなく、書店に足を運ぶことが重要です。
大きな理由が二つあります。
一つ目は「類書」の調査です。
確かに中身の一部閲覧や試し読みが、インターネットで出来るようにはなりました。
ただし、全部ではありません。解った気になっていると思わぬところで、足をすくわれます。
敵=類書はどんな章立て、内容、デザイン、紙質で顧客のハートを射止めているのかを、現物を手にして確かめなくてはいけません。
二つ目は「棚」の調査です。
意外と気がつく人は少ないのですが、本は分野別に並べられるのです。
ビジネス、資格、自己啓発、健康、料理、マーケティング…。業界では「棚があるか、無いか」という表現をします。
出版した本を並べる棚が、あるのかないのかという意味です。
棚があるというのは、取り扱いが多い分野、ないというのは取り扱いが少ない分野です。
例えば社労士の方。
社労士試験に受かるノウハウを公開するとしたら、資格の棚、人事労務トラブル防止と事例であれば、人事・労務の棚、
もしかしたら社労士という資格は別にして、自分のウツ克服と医者選びについて書きたいと言う方もいるかもしれません。
すると、健康??。
では、自分と同じ棚には、どんな本があるのか?そもそも、あなたの出した本が載る棚は、書店でどのくらいの場所を確保しているのか?
棚面積=シェアです。
よって、自分は小さな市場を選び、占有率で勝負するのか、それとも大きな市場を選び母数の多さで良しとするのか?
私は、同じコンテンツでありながら、切り口を変えて棚を変えると言う裏技を使うことがあります。
例えば、整骨院の先生の肩こり本。
健康分野だろうと言うのが一般的ですが、あまりにも類書が多すぎて埋もれてしまう場合には、
フランチャイジー展開や資格取得という切口で勝負することもできます。
ちょっと、高度ですね。
後者については、特に処女出版の方には重要です。
出版社は一冊出すために300万円のリスクを負うと言われています。
また、在庫を抱えると倉庫代がかさみます。
一定期間がたった本は裁断されてしまうのですが、これにもお金がかかります。
よって、売ることが重要です。
最近は、編集会議で編集担当者がコンテンツも著者の人柄もいいので出したいと言っても、
営業担当者が著者に売る気がない、類書が多くて売れないと反対したので結果としてボツになった…
という例が増えています。
私も、出版社側から販促計画を添付してください。と言われたことが幾度もあります。
ところが著者の方に依頼したものの「作り方がわからない」「どうやって売るのか想像できない」と
返事をされてしまい、出版社からこのままでは絶対にボツです、と言われてしまいました。
結果として私が事業計画に合わせて作成し、無事企画会議を通すことができました。
自分でセミナーを開催するとか、お客様にキャンペーン商品として販売するとか・・・。
ちょっとした工夫と熱意があればいいことなのですが・・・。
————————————————————————————————————-
さて、その 企画書の書き方 ですが、項目は、いたってシンプル。
—————————————————————————————————————————
1) タイトル ・・・ 内容が分かるもの。だたし、後から変わることもあり。
2) 出版目的 ・・・ なぜ今このタイミングで、この著者が出さなくてはいけないのかを訴求。
3) 本の概要 ・・・ 簡潔に。
4) 読者ターゲット ・・・ 誰でも、はダメ。
事業に役立つことを考えるのであれば、絞り込む方がベター。
私は、一万人の誰かではなく、3000人の見込顧客に読んで頂くようにして下さいとアドバイスをしています。
5) 目次 ・・・ 章立て。五章から七章が標準。各章の中に項目立て。
見本原稿を依頼されることもあります。
この場合、目次の中から「一番得意な部分」を1500~2000文字程度書いてください。
内容だけではなく、文章の品質も問われますので助詞づかい、言い回しにも細心の注意を配りましょう。
…………………………………………………………………………………..
5.出版を最強の事業戦略にするコツ
………………………………………………………………………………….
「やっと本になりました」嬉しいですね。
でもほんとうは、ここからがスタートです。
アマゾンキャンペーンに走る人が多いのですが、実は顧客獲得や事業展開に寄与するかというと疑問です。
出版社やPR会社もここは熟知していますから、アマゾンキャンぺーン何位と名刺に書いても、評価はさほどしてくれません。
大切なのは、顧客となるであろう人に、長期間訴求し続けること。
そして、買って頂いた本がいつまでも所持されていることです。
即、ブックオフに行ってしまっては口コミになる可能性も低くなります。
事業展開に直結させる方法を二つご紹介します。
まず一つ目は、配本調節です。
書店ルートを活用した出版、つまり電子書籍と本屋におかない自費出版以外であれば、どんな分野にでも当てはまります。
最近はアマゾンで買う人が多いと考える著者が多いようですが、まだまだシニア層や主婦は買い物帰りに
書店によったり、大学生は学生生協でと、アナログ販売には独特の根強さがあります。
これを活かします。
例えば、小学生の子供を持つママさん向けに訴求したい場合。
都内の大型書店よりも、100円ショップやスーパーで安価に量販する仕組みにした方が、
顧客層の手元に届く確率は高まります。
本における売り上げは大きくないかもしれませんが、その中に自社の連絡先やQRコードを埋め込む
などしておき、フロント商品として活用できます。
若手のビジネスパーソンを対象にしたいとするならば、コンビニエンスストアに置く事もよいですね。
地元密着型の老舗企業の場合、自社の近くの本屋に集中配本することもブランディングにつながります。
「あの会社の会長さんの本が、○○書店にあったよ」などという口コミ効果も期待できます。
二つ目は、タウン誌とのコラボレーション。
こちらは地域密着型のビジネスが対象となります。
20代のOLの方たち、あるいは主婦層の方に効果大です。
本の内容を講演会やセミナーとして企画し、それをタウン誌と共催することができます。
先着五名様に書籍を無料プレゼントなどとうたうのもいいでしょう。
この際に、注意しなくてはならないのが、タウン誌の読者メリットです。
参加したものの本を買わされた、商品の説明だけで終ったという企画になってしまうとあなたではなく、
タウン誌の会社にクレームが行きます。
もちろん、広告をだすという一般的な方法がありますが、このときでも本を出しているかいないかによって
顧客反応に大きな差が出ます。
歯科医や美容整形、エステサロンなどは同業社が紙面上で競っていますが、
その中で「所長は本を出しています」と一冊片手にしている写真を掲載するだけで
顧客は間違いなくあなたの会社に信頼を寄せて、流れてゆきます。
少しパターンは異なりますが、私が
ドトールコーヒーのフリーペーパーに記事として取り上げられた事例
をご紹介します。
広報部の方が、私の「十年後の名刺」(二見書房)という本を読んで下さった後、
ぜひ自社が発行している顧客向けのフリーペーパーの図書紹介に掲載したいと申し入れがありました。
もちろん、願ってもない良いお話です。
小さな枠ですが、本の写真と自社名とURLを入れて全国の店舗に配置してくださいました。
すごい数!もちろん無償です。
弊社のように、人材も資金も限られている小さな会社には嬉しい限りです。
本を出したからこそ出来た、広報だと思っています。
その後、韓国でも同書が翻訳出版となりました。
これは韓国の経営者の方たちと打ち解けるための、良い話材となっています。まさに「本の使い方」です。
最後に、電子がいいか、紙がいいか、という質問を受けますが、比べること自体がナンセンスです。
みなさんのターゲットとする読者が、どちらをよんでいるかということが重要です。
ただ、私が紙をお勧めするのは「手で渡す」「顔を突き合わせて」「表紙にひと言書き添える」というさまざまな、心のこもったコミュニケーションツールとして活用できるからです。
なお、この数年はマスコミが報じているほど、インフラが整っていないということも頭の片隅に入れて頂いた方が良いかもしれません。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
崎山さんのお話はいかがでしたでしょうか?
「本を出して、自社のブランド創りに利用したい、マーケティングに利用したい」と考えている方は
多いと思います。
その際、どのように進めればよいのでしょうか?
自分で企画書を作って出版社に持ち込みますか?
あるいは、自費出版にしますか?
自分で企画書を作って出版社に持ち込んでも、採用される可能性はかなり低い、
ということは崎山さんの講演にありました。
かといって、自費出版すると300万円ぐらいかかりますし、発行後に書店で販売してもらえる可能性はほとんどありません。
書店で販売してもらえない本を作ってしまうと、初版3千部の大部分を自分で保管することになります。
こんなに本ができてしまうと、実際問題、置く場所の確保だけでも大変です。
そして、何よりも、この出来上がってしまった本はいったいどのように使えばよいのか、別の悩みが産まれてしまいます。
結局、本を出版したいと思ったら、最初から、どのような企画を、どこの出版社に持ち込み、
どのように流通させ、さらに、その本を使って、自分または自社のブランド創りのためのどのように活用する、
といった結構綿密なシナリオを用意しておかないと、単なる自己満足のための出版で終わってしまう、
というのがよくあるパターンではないかと思います。
私がクライアントに対して、本の出版をお勧めする場合、基本的に、
クライアントの商品や企業をブランド化すること、クライアントのマーケティングに活かすこと、が目的です。
本の出版そのものが目的なのではありません。本を出版してからが重要、ということです。
今回、崎山さんの講演をご紹介したのは、私の出版に対する考え方、
つまりマーケティング戦略の一環としての出版、という考え方にピッタリとあっていたためです。
もし、本の出版を自社のブランド化、自社のマーケティングに活用したい、というニーズがあれば、一度、
お問い合わせいただくほうがよいと思います。
本件に関するお問い合わせは、コラム上部のお問い合わせもしくはこちらからお願いします。